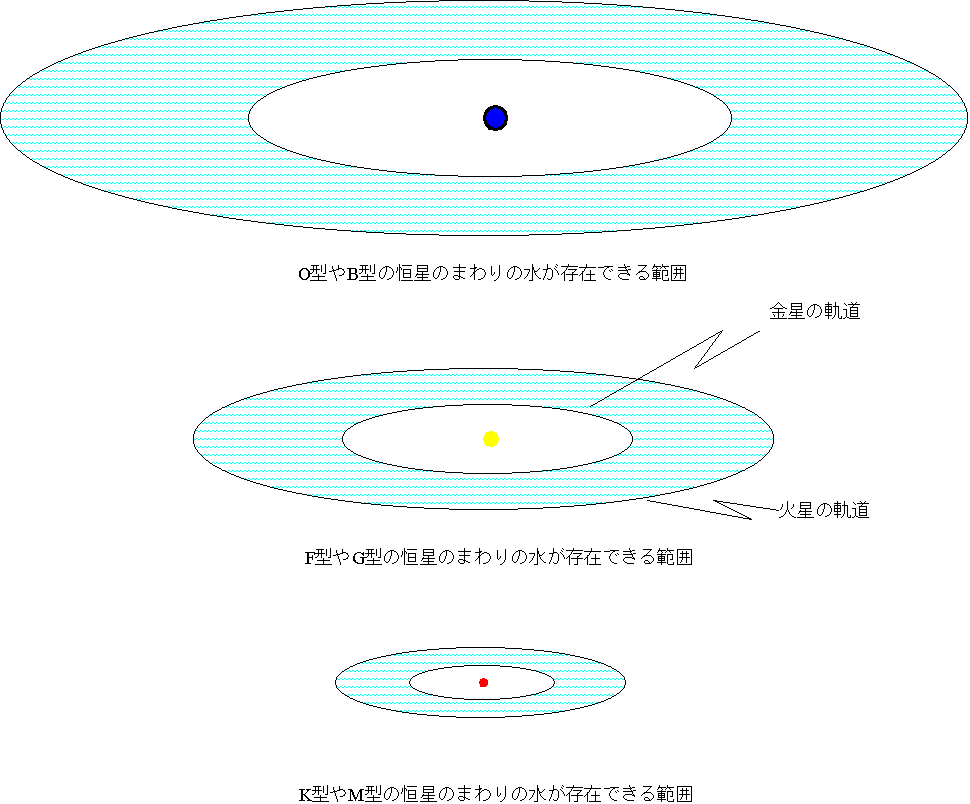
第3章 大気と海の起源−水惑星の誕生−
| 目次 | |
| 1. | 大気と海の起源 |
| 2. | 水惑星の誕生 |
| 用語と補足説明 | |
| この章の参考になるサイト | |
1. 大気と海の起源
原始地球は、水素やヘリウムというガスが存在する中で集積する。そして、その大きさが月を超えたあたりから、こうしたガスを保持できるようになる。つまり、原始地球の大気は太陽の組成や木星型惑星の組成に似た水素、ヘリウムを主成分とする大気であったかもしれない。こうした大気を太陽組成大気(いわゆる一次大気)という。
だが、現在の大気ははこうしたものとは大きく違っている。つまり、地球の大気は原始太陽系星雲のガスを捕獲したものではなく、固体地球内部からの脱ガス(衝突脱ガス大気、いわゆる二次大気)によるものである。そもそも、原始地球初期の激しい微惑星衝突の時代には、原始太陽系星雲のガスを捕獲できたとしてもそれは一次てきなもので、高温になった表面からはすぐに宇宙に逸散するであろう。少なくとも、その時点で原始地球や微惑星からの脱ガス成分と混じってしまう。そうした意味で、「一次大気」という言葉は、地球の原始大気は太陽組成のものであったはずであるという前提があるので、あまり使われれなくなってきている。
では、原始地球からの脱ガスの組成はどのようなものであったのだろう。ここでもいん石が重要なヒントを与える。いん石の中にはH2Oを鉱物の形で持っているものがある(鉱物の結晶中に水分子としてH2Oを固定している、これを含水鉱物という)。ほかに、NやCも含まれる。とくに炭素質コンドライトの中には、H2Oを6%も含むものがある。地球の材料となった微惑星全体を平均しても、1%くらいのH2Oが含まれていたと考えられる。現在の地球の海水の質量は、地球の質量の0.027%である。つまり、微惑星の中のH2Oの40分の1が脱ガスすれば量的には充分ということになる。
微惑星が原始地球に衝突するとその衝撃で加熱され、微惑星や原始地球の鉱物の内部に取り込んでいたH2Oをはじめとする揮発成分(気体になりやすい成分)が吐き出される(脱ガスする)ことになる。そのときの組成はどのようなものであろうか。ここでマグマオーシャンが大きな役割を果たすことになる。
マグマオーシャンが存在すると、マグマオーシャンに溶けやすいH2Oの大部分はその中に溶け込んでしまう。残った大気や溶け込んだ大気はマグマオーシャンと反応する。マグマオーシャンの中に金属鉄が残っていれば、鉄がH2Oから酸素を奪って鉄は酸化鉄になり、H2Oは還元されて水素になる。こうして、大気は水蒸気よりも水が、二酸化炭素よりも一酸化炭素が多い状態になる。
しかし、マグマオーシャンに金属鉄がない状態ではそのようなことが起きない。つまり、核とマントルの分離が起こってしまったあとではH2O(水蒸気)や二酸化炭素という形での脱ガスということになる。一酸化炭素(CO)があったとしても、H2O(水蒸気)と反応して、二酸化炭素(CO2)と水素(H2)になる。核とマントルの分離は地球のごく初期の段階で起きたと考えられているので(地球誕生参照)、脱ガスの主成分もH2O(水蒸気)や二酸化炭素ということになる。水素は軽いので、地球の重力では保持できずに宇宙空間に逸散することになる。
また、地球集積の終わりの方で、H2Oをたくさん含む炭素質コンドライトや彗星の集中的な衝突が起こった可能性もいわれている。マグマオーシャンが冷えてくると、溶け込んでいたH2Oも脱ガスしてくる。
こうした脱ガスは地球の初期の段階に集中的に起きて(カタストロフィック脱ガス)、その後の脱ガス(現在では衝突脱ガスではなく火山ガス)は細々と現在も続いている。マグマオーシャンから鉄が失われてから(核とマントルの分離以降=地球のごく初期以降)の脱ガス(火山ガス)の組成は現在とそれほど変わらないと考えられる。じっさい、火山ガスの主成分はH2O(水蒸気)やCO2(二酸化炭素)である。
2. 水惑星の誕生
激しい微惑星の衝突の時代が終わると、地球はだんだんと冷えてくる。そしてそのときの大気の主成分であった水蒸気は水となり海ができる。海ができると大気中の水に溶けやすい成分はその中に溶け込むことになる。大気中に二番目に多い気体であった二酸化炭素も水に溶け込む。そして、海水中のCa(カルシウム)やMg(マグネシウムと)と反応して石灰岩(炭酸塩鉱物)となり地殻に固定される。こうして、大気からは二酸化炭素が取り去られていく。
現在の火山ガスに含まれているSO2(二酸化イオウ)、塩化水素HCl(塩化水素)などが水に溶ければ硫酸、塩酸になるが、こうした強酸は岩石を溶かすことによって間もなく中和されていく。
結局、地球の大気は水に溶けにくいN2(ちっ素)が主成分となる。これは、表面に液体の水(海)を持たない他の地球型惑星の大気とは対照的である。これについてはこちらも参照。
現在の地球大気中二番目に多いO2(酸素)は、生命の発生以後、生物(植物)の光合成によってつくられた酸素がたまったものである。これについてはこちらを参照。
どちらが安定か:マグマ中の気体の反応は下のようなものである。ここで、CH4はメタン、NH3はアンモニア。
2H2O ←→ 2H2+O2
2CO2 ←→ 2CO+O2
CO2+4H2 ←→ CH4+2H2O
N2+3H2 ←→ 2NH3
鉄が存在しているときは(核とマントルの分離以前)は右辺が安定であるが、鉄がなくなると左辺が安定になる。上に書いたように、核とマントルの分離は地球誕生のかなり早い段階で起きたと思われているので、脱ガス成分は左辺ということになる。少なくとも、生命が誕生するころの地球の大気はCH4やNH3に富んだいわゆる還元的な大気ではないことは、ほぼ確実である。CH4やNH3に富んでいると、有機物(生命の材料)の合成には有利なのであるが。
液体としての水の存在:惑星の表面に水が存在できる条件を考える。恒星に近すぎると熱すぎる、遠すぎると寒すぎる。つまり、ちょうどその中間あたりということになる。太陽系では金星の軌道付近が近い方の限界、火星付近が限界と考えられる。金星にもかつては水があったのかもしれないが、熱暴走を起こして現在の姿になったのかもしれない。これについてはこちらも参照。火星にはかつて表面に水があった可能性は高いが、現在ではない。
表面温度が高いO型やB型の恒星のまわりの水が存在できる適温範囲は、太陽のようなG型の恒星よりはるかに広い。つまり、そこに惑星が存在する確率が高い。しかし、O型やB型の恒星の寿命は短い。K型やM型の恒星は寿命が長い。しかし表面温度が低いので、液体としての水が存在できる適温範囲が狭いので、そこに惑星が存在する確率が低い。
つまり、O型、B型の恒星のまわりの惑星上で生命が進化するためには、時間が足りない。逆に、K型やM型の恒星は寿命が長いので、生命の進化のための時間は充分あるが、そもそも適温範囲に惑星が存在する確率が低い。つまり、生命が存在する確率も低い。
だからF型、G型の恒星が生命の発生・進化に適している、生命を探すならF型、G型の恒星のまわりを回っている惑星がいいということになる。
もっともこれは議論が逆立ちをしていて、液体の水の存在を前提とする「地球型生命」にとって、そうした地球の上で発生・進化したきたのだから、こうした環境に適しているのは当たり前のことでもある。
なお、恒星のO型などのスペクトル型ついてはこちらを参照。恒星の寿命についてはこちらを参照。
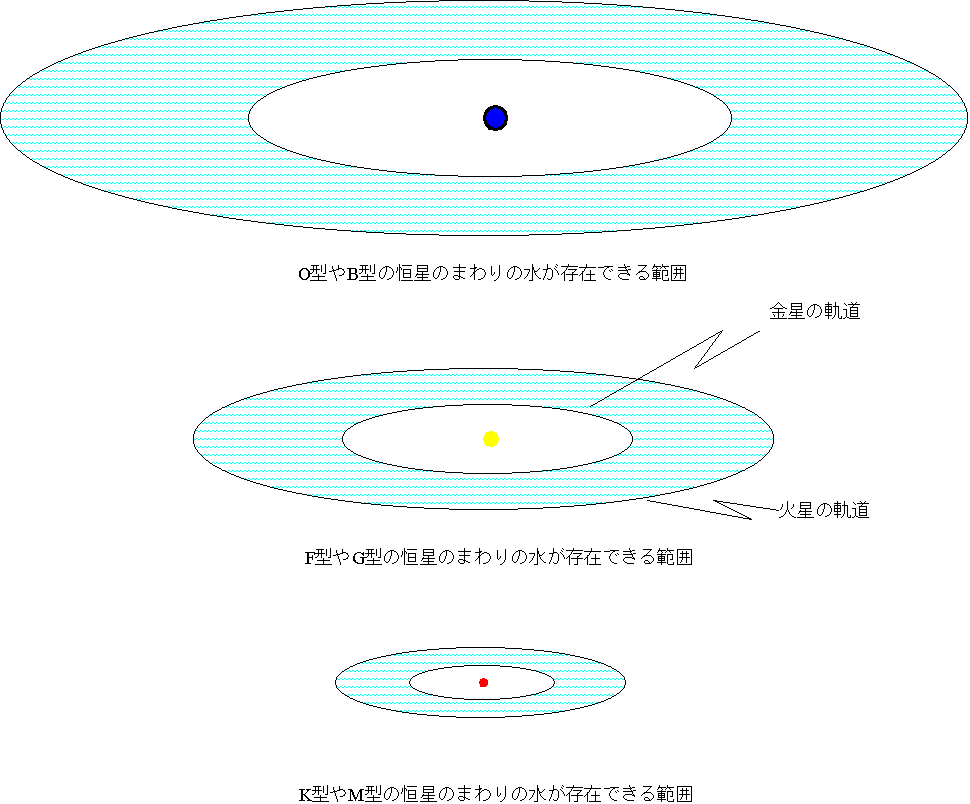
他の地球型惑星の大気:大気がほとんどない水星をのぞき、90気圧という分厚い大気を持つ金星大気の主成分はCO2(二酸化炭素、96.5%±0.8%)であり、薄い火星の大気の主成分もCO2(95.32%)である。二番目に多い気体は両惑星ともN2(ちっ素)である。つまり、この両惑星は海(惑星表面の水)が存在できなかったために、つまり水蒸気も存在できなかったために、二酸化炭素が大気の主成分になったのである。火星は表面重力が小さいために、大気のほとんどを失ったと考えられる。地球も石灰岩として固定されている二酸化他炭素の量は、30気圧〜50気圧分と考えられている。これについてはこちらも参照。
二酸化炭素の循環:大気中のCO2は水に溶けて、H2CO3(炭酸)となり、地球表面の鉱物を溶かす。これが化学的風化(の一つ)である。たとえば石灰岩(CaCO3、厳密には方解石)は
CaCO3+CO2+H2O → Ca2++2HCO3- …(1)
つまり、大気中のCO2は、直接海に溶け込むばかりではなく、風化によって炭酸の形で海水に溶け込み、大気から取り除かれていくことになる。また、海水中に移動した(Ca2++2HCO3-)は、
Ca2++2HCO3- → CaCO3+CO2+H2O …(2)
と石灰岩(方解石)として沈殿する。つまり、(1)(2)式を合わせ見ると、結局(1)で大気からのぞかれたCO2は、同じ量が(2)で大気に戻ることになる。だが、風化されるのは石灰岩ばかりではない。地表では次のようなケイ酸塩の風化もある。SiO2は石英(岩石ではチャートに近い組成)。
CaSiO3+2CO2+H2O → Ca2++2HCO3-+SiO2 …(3)
(3)と(2)から、 CaSiO3+CO2 → CaCO3+SiO2 …(4)
としてこれも考えると、風化作用→石灰岩の沈殿により、大気からCO2が取り除かれることがわかる。
だが、海底でできた石灰岩はプレートの運動により、マントルに沈み込んで熱せられ、火山ガス中のCO2となって再び大気に戻る(一部は陸地に付加して石灰岩の岩体になる)。
マントルから大気に戻るCO2の量は一定であるが、風化の速さ(上の化学反応の速さ)は、そのときの地球の温度が高いほど速く、温度が低いと遅い。つまり、何らかの原因で地球の温度が上がると、大気中のCO2が取り除かれる量の方が、火山ガスとして大気に戻る量よりも多くなる。これによって大気中のCO2が減り、CO2による温室効果も小さくなって、地球の気温は下がる方向(もとに戻る方向)に変化する。何らかの原因で、気球の気温が下がったときは逆に地球の気温が上がる方向に変化する。このCO2の循環により、地球の温度は一定に保たれる、つまり負のフィードバックが効いていることがわかる。
生物の発生以後のCO2の循環や、負のフィードバックについてはこちらを参照。