
かに星雲(国立天文台):http://www.nao.ac.jp/Gallery/Messiers/m1rgb.jpg
2. 超新星
今まで恒星が見えなかったところに、急に恒星が見えだすことがある。これが新星であり、恒星の爆発現象である。その中でもとくに明るいものを超新星という。ただ、これは本当に突然に新しい恒星が誕生したのではなく、今まで見えなかった恒星が爆発などによって突然に明るく輝きだすことによって、あたかも新しい恒星が誕生したように見えるのである。そのごゆっくりと暗くなっていく。
超新星は、恒星の最期を飾る大爆発である。太陽はこれまでの約50億年間で1043J程度のエネルギーを放出してきたが、超新星はほぼ一瞬でその10倍程度のエネルギーを放出する。そのときの明るさは、一つの超新星の明るさが一つの銀河に匹敵する場合もあるといわれている。もっとも超新星爆発を起こす恒星の質量は太陽よりかなり重い恒星で、太陽程度の質量の恒星の最期はこれほど華々しいものではない。これらは恒星の進化を参照。
この大爆発によって、恒星自身の大部分は吹き飛ばされる。また、炭素、酸素、ネオン、ケイ素、カルシウムなど、さらには鉄よりも重たい元素が合成され、それらが宇宙にまき散らされる。鉄よりも重たい元素は、ふつうの恒星の中心部で行われている核融合反応では合成されないので、この超新星の爆発によってできたものである。われわれの地球(太陽系)には、鉄よりも重たい元素が存在している。これは、われわれ太陽系を構成している元素は、かつてどこかの超新星爆発によってできた元素であることを示している。これらについては、<第一部−1−宇宙の歴史?の「第2章 物質の起源」<b.さまざまな元素の生成>、<c.鉄よりも重たい元素の生成>を参照。
われわれの銀河系内での超新星爆発は、西暦185年以降、少なくとも8回起きているという(「天文の事典」(平凡社))。中でも有名なのは、1054年のものであろう。日本では平安時代のことだが、鎌倉時代の歌人藤原定家(1162年〜1241年、だから藤原定家は実際に見たわけではない)の「明月記」に記録が残っている。それによると、「オリオン座の隣、おうし座あたりに、木犀ほどの大きさ(明るさ?)に見えた」という。中国に残っている記録を総合すると、出現後20日間程度は昼間でも見えたという。
この超新星の爆発によってまき散らされた物質は、現在かに星雲としてみることができる。かに星雲は猛烈な勢い(数千km・s-1)で膨張しているが、その膨張を反転させるとまさに1054年に一点に集まる。だから、たしかに1054年に爆発があり、その後膨張しているということがわかる。

かに星雲(国立天文台):http://www.nao.ac.jp/Gallery/Messiers/m1rgb.jpg
その後、1572年に出現したものはチコ・ブラーエ(1546年〜1601年)が、1604年に出現したものはケプラー(1571年〜1630年)が観測している。
この1604年の超新星以来、われわれの銀河系内では超新星爆発は起きていない。しかし、平均的な銀河では50年に1回程度では起こるといわれている(「天文の事典」(平凡社))。じっさい、隣の大マゼラン星雲では1987年に出現している。大マゼラン星雲は日本からは見ることはできないが、この超新星爆発のときに同時に放出されたニュートリノは地球を貫き、岐阜県に設定されていたニュートリノ観測装置カミオカンデ(スーパーカミオカンデの前身)で捕捉されている。この超新星の写真はハッブル宇宙望遠鏡のサイトで見ることができる。
なお、超新星にはI型とII型がある。
3. パルサー
規則正しくとても短い時間(数千分の1秒〜長くても数秒の周期)で電波を出す天体が発見され(1967年)、パルサーとなづけられた。このパルサーの正体は、超新星の爆発で残った中心部である。かに星雲の中心部にも、0.033秒の周期で電波を出すパルサーがある。
超新星の爆発の際、中心部が吹き飛ばされずに残ることがある。この中心部はもはや核融合反応は行っていないので、自分自身の重さでつぶれてしまう。白色わい星も超高密度ではあるが、まだ原子の構造(原子核(陽子と中性子)−電子という構造)で自分自身を支えている。ところが超新星爆発で残ったこの中心部のではそれすらもできない。つまり原子の構造さえもが壊れてしまうのである。原子の構造が壊れるとは、電子が原子核(の中の陽子)に吸収されてしまうということである。電子(マイナスの電荷を持っている)を吸収した陽子(プラスの電荷を持っている)は中性子となる。つまり星全体が中性子となってしまう。だから、パルサーは中性子星とも呼ばれる。このときの密度は、1012kg・m-3(角砂糖程度の大きさである1cm3が10億トン)にもなっている。太陽程度の質量の恒星が、半径10km(もとの半径の7万分の1)くらいにまで縮まった感じである。原子はすかすかなので、この構造がつぶれてしまうと大変な超高密度になるのだ。
また、回転している物体は、縮むと自動的にその回転が速くなる。ちょうど、フィギアスケーとの選手がスピンを行うとき、最初手を大きき広げている格好から、手をすぼめる(両手を頭の上で合わせる)と、自動的に回転が速くなるのと同じである。だから自転していた恒星が、パルサーのサイズまで縮まると1秒間で何百回転にもなるのだ。
恒星が縮むとき、磁場も縮み、その磁場は地球磁場の1兆倍という途方もない大きさになる。そしてこの磁極が自転軸と一致していないと、指向性の強い電磁ビームが放射される向きも自転とともに回転する。そしてそのビームの向きに地球が来たときだけ電波を受け取ることになるので、パルサーとして観測される。
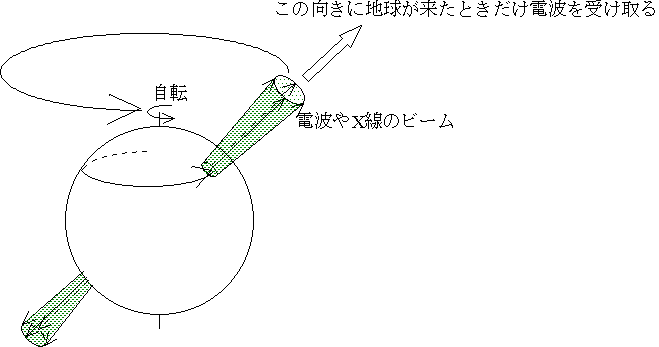
じつは中性子星は、1932年アメリカのオッペンハイマーによってその存在が予想されていた。35年後に実際に発見されたことになる。
4. ブラックホール
パルサー(中性子星)は、中性子が支えている。では、中性子でも支えきれないくらいにまでつぶれたらどうなるのだろう。天体の表面からの脱出速度(その天体の引力を振り切り、無限の彼方まで飛んでいくことができる最低の速さ)は、天体の質量が一定ならば天体の半径の平方根に反比例する。つまり、半径が4分の1になれば2倍に、9分の1になれば3倍にと大きくなっていく。太陽表面からの脱出速度620km・s-1である(地球表面からは11.2km・s-1)。太陽が半径10km程度(70000分の1)にまで縮まれば(パルサー程度の大きさになると)、その表面からの脱出速度は70000の平方根倍(260倍)。これは光速の半分以上の1.6×105m・s-1になる。さらに、半径が3km(太陽の半径の230000分の1)程度にまで縮まってしまうと、脱出速度は230000の平方根倍(480倍)の3.0×105m・s-1にまでなってしまう。
3.0×105m・s-1といえば、これは光の速さ(光速)である。つまり、太陽程度の質量の恒星が半径3kmよりも小さく縮んでしまうと、その表面からは光速でも飛び出すことはできなくなる。この宇宙は光速よりも速いものはないとい宇宙である。つまり、光もその仲間である電磁波、あるいは重力などが伝わる速さがこの宇宙では一番速く、それ以上のものはないし、どんなに工夫をしても、あるいはエネルギーを与えたも、そうした速さを越えることはできない。つまりそれほどまでに縮んでしまった天体の表面からは、光を含めて何も出てくることはできない。これがブラックホールである。ブラックホールの中の一切の情報はわれわれには永遠に届かない。つまり、その中の世界はわれわれとは無関係なものである。
ブラックホールからは何も出てこないので、もちろん見ることはできない。しかし、ブラックホールの回りのガスがブラックホールに落ち込みとき猛烈に熱せられて、その超高温のガスが発する電磁波(超高温の物体から出る電磁波はX線)がある。つまり宇宙に強いX線源があれば、その近くにブラックホールがある可能性があるということになる。その候補の一つとして、白鳥座X-1というX線源があり、その近くにはブラックホールがあるのではないかといわれている。
もしかするとわれわれ銀河系の中心部にも、巨大なブラックホール(大質量ブラックホール)があるのかもしれない。
超新星のタイプ:タイプIは、外側の水素の層を失った白色わい星の表面に、連星系の相手である巨星から放出されて降り積もったガスの重さにより、内部の炭素の核融合反応が暴走して起こる。この際に大量の鉄元素が合成される。炭素爆発型ともいう。タイプI型の超新星が一番明るくなったときは-18等〜-19等くらいと一定なので、もしこうした超新星が遠い銀河で現れると、その見かけの明るさと比較することによって、その銀河までの距離を求めることができる。
タイプIIは、太陽の8〜10倍以上の質量の大きな恒星で起こる。こうした質量の大きな恒星では、水素、ヘリウム、炭素、酸素、ネオン、ケイ素の原子核が次々に反応し、中心部では鉄がたまっている。鉄は核融合反応を起こさないので、これがたまってある量を超えると、自分自身の重さでこの鉄の芯が崩壊しして、まわりの物質が一挙に中心部に落ち込んでくる。そしてその反動で大爆発を起こす。鉄崩壊型ともいう。
現在では超新星の研究が進み、より細かい分類もなされている。
オッペンハイマー:オッペンハイマー(1904年〜1967年)はアメリカの物理学者。ブラックホールの存在も予言している。湯川秀樹(1907年〜1981年、1949年日本最初のノーベル賞受賞)が予想した中間子などについてもコメントしている。アメリカの原爆製造計画(マンハッタン計画)で中心的な役割を果たしたが、戦後水爆製造への協力を拒否したため公職を追放される(1954年)。1964年にエンリコ・フェルミ賞を受賞し、名誉を回復する。
ブラックホールの半径:ある天体の質量が決まれば、下のようにどこまで縮まるとブラックホールになるかの式を求めることができる。下の式からブラックホールになる半径は天体の質量に比例することがわかる。例えば太陽の質量の10倍の恒星は、太陽程度の質量だと半径3kmでブラックホールになるわけだから、その10倍の半径30kmにまで縮まればブラックホールになることがわかる。
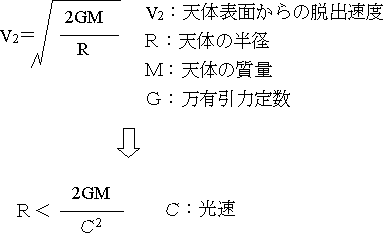
この半径をシュバルツシルト半径という。本当はシュバルツシルト半径は一般相対性理論から導き出されるのであるが、上のようにニュートン力学に従って求めたものと同じになる。シュバルツシルト(ドイツの天文学者)はアインシュタイン(1879年〜1955年)が一般相対性理論を発表した翌1916年にはもうこれを発表している。
超新星について
高エネルギー加速器研究機構:http://www.kek.jp/kids/class/cosmos/neutrinos.html
富山市科学文化センター:http://www.tsm.toyama.toyama.jp/curators/aroom/var/sn.htm
ブラックホールについて
神戸大学松田卓也教授:http://www.edu.kobe-u.ac.jp/fsci-astro/members/matsuda/review/blackhol.html
宇宙航空研究開発機構:http://spaceinfo.jaxa.jp/note/shikumi/j/shi101_blackhole.html