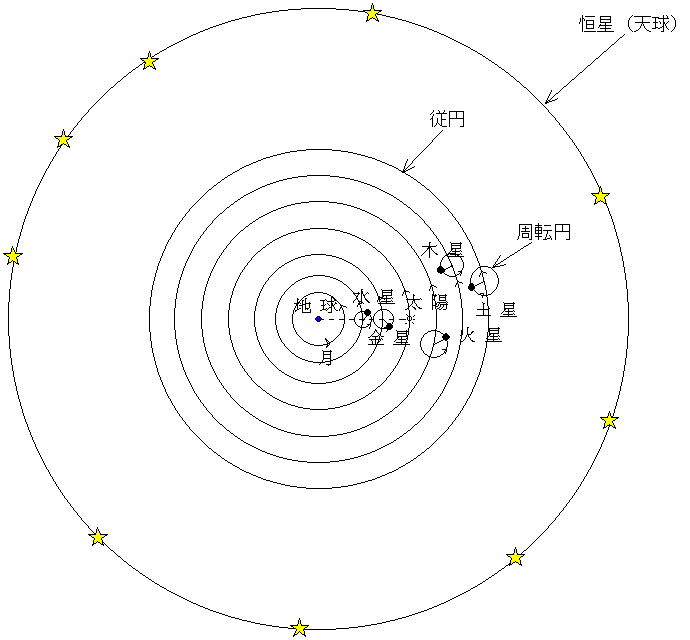
d.天動説と地動説
d-1 天動説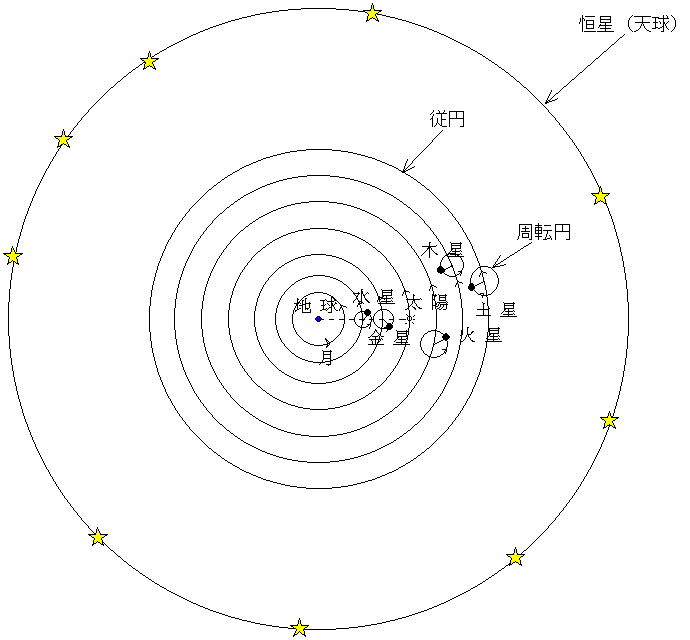
地球が動いていることはもちろん、大地(地球)が丸いことも実感としてはわからない。だから昔の人たちが円盤の地球を考え、そのまわりを太陽や他の天体すべてが回っていると考えるのは当然であった。
昔の人は、地球が宇宙の中心で、他の天体は太陽も、惑星も、恒星もすべて地球のまわりを回っていると考えていた。この地球中心の考えを天動説という。天動説をきちんとまとめたのは、プトレマイオス(ギリシャ、100?〜170年?、英語読みではトレミーとなる)である。
彼のモデルは非常に精密なものであった。宇宙の中心に地球があり、そのまわりを月、水星、金星、太陽、火星、木星、土星の順に回っている。そして水星、金星、火星、木星、土星の各惑星(当時はこの5つしか知られていなかった)は、単純に地球のまわりを回っているのではない。まず地球のまわりの大きな円(従円)に中心を持つ小さな円(周転円)を考え、各惑星は周転円上を回っている、そして周転円の中心は従円上で地球のまわりを回っているというものである。さらに水星と金星の周転円の中心は、つねに地球と太陽を結ぶ線上にあるという制約を設ける。
恒星は一番外側にあって、一つの球殻(天球)に貼付いて、お互いの位置関係を変えずに(星座をつくったまま)、その天球が地球のまわりを回っている。
地球(+月)と太陽を入れ替えれば、今日の太陽系のモデルとそう変わりはない。
惑星の複雑な見かけ上の運動を説明するために、プトレマイオスはこのような複雑なモデルを考えた。でも、こうした複雑なモデルを使えば、惑星の運動を含め、天体の運動を説明できるである。決して荒唐無稽な説、観測事実を無視した説ではない。
惑星の運動で難しいのは、天球上での順行・逆行という見かけの動き(視運動)である。これが周転円を使うことによって説明できてしまう。また、水星と金星が最大離角を持つ(太陽からはあまり離れた位置に見えない、真夜中には見えない)ということも、水星・金星の周転円の中心がつねに地球と太陽を結んだ線分上にあるとすれば説明がつく。当時の社会的な要求からして、これで十分な精度で天体の運行を予想できるので、それ以上のものは必要なかったともいえる。
このような実用性以外にも、プトレマイオスの理論は、中世のヨーロッパにおいてはキリスト教公認の理論となった。このために、プトレマイオスの理論に異議を唱える者は、キリスト教(教会の権威)に異議を唱える者とみなされ(異教徒が何をいっても無視すればよいが、同じキリスト教徒の中では「異端」として厳しく扱われる)、場合によってはブルーノのように死刑にまでなった。このためもあって、プトレマイオスの地球中心の理論、すなわち天動説は千数百年に渡って、支配的な理論となったのである。
※ 惑星の視運動についてはこちらも参照。
d−2 地動説
地球が太陽のまわりを回っているという考えが地動説である。一番最初に地動説を唱えたのは、紀元前3世紀ころの古代ギリシャのアリスタルコスだといわれている。彼は巧妙な方法で、地球−月の距離に対して地球-太陽の距離が何倍になるか、また太陽の大きさは地球の何倍になるのかを求めた。アリスタルコスとその方法についてはこちらを参照。
アリスタルコスは、太陽が地球の10倍もの大きさを持つ巨大な天体であることを知り、そのような巨大な太陽が地球のまわりを回るのは不自然であると考えた。そして、小さな地球の方が太陽のまわりを回っているという説を唱えた。しかし、アリスタルコスはプトレマイオスのような精密な、実用に耐える太陽系のモデルをつくることができなかった。こうして実用性においても、またヨーロッパにおいてはキリスト教の教会との関係においても、アリスタルコスの説は受け入れられなくなり、次第に忘れ去られていった。これとともに、ギリシャ時代にはほぼ正確に大きさまでも求められていた丸い地球という概念も忘れられていった。
しかし、コロンブス(イタリア、1451年〜1506年)に代表される遠洋航海者たち、地球は丸いというと考える航海者たちが15世紀の後半から増えてくる。彼らは陸が見えない外洋では、天体観測で自分の位置を求めていた。しかし、どうもプトレマイオスの理論をもとにした天体の位置の表は誤差が大きい。また、計算も複雑である。もっと、簡単で正確に自分の位置を求める方法はないのかという要求が高まっていった。
こうした中、コペルニクス(ポーランド、1473年〜1543年)が登場する。彼は天動説に疑問を持ち、アラビア経由で持ち込まれた古代ギリシャの文献を読むうちに、アリスタルコスの考えを知った。そして確かに、太陽のまわりを各惑星が回っているとした方が簡単に、そして正確に惑星の位置を計算できることがわかった。こうして彼は、地球を宇宙の中心の座から引きずり降ろし、太陽中心の「地動説」を唱え、「天体の回転について」(1530年)という本を書いた。もっとも、実際に出版されたのは彼の死後である。また、全体のトーンとしては、太陽を中心にした方が簡単に説明がつくというものであり、本当にそうだという感じで書かれてはいない。
ともかくこのコペルニクスによって、これまでの宇宙観が根本的にひっくり返ったので、こうした考え方の大きな転回を「コペルニクス的転回」という。
その後、この地動説を支持し、宣伝して回ったために火刑に処せられたジョルダノ・ブルーノ(イタリア、1548年ころ〜1600年)のような犠牲者も出しながらも、また、チコ・ブラーエ(1546年〜1601年)のように年周視差が測定できないということから「実証的に否定」するものもいる中、ガリレオ・ガリレイ(イタリア、1564〜1642年)、ケプラー(ドイツ、1571〜1630年)、そしてニュートン(イギリス、1642〜1727年)などの理論家たちによって、地動説は現代につながる確固たる宇宙観になる。またケプラーが作成した惑星の運行表「ルドルフ表」は航海者の役に立ったばかりではなく、のちのニュートンが惑星の運動を考える、すなわち万有引力の発見にも大いに力になったのである。
地動説の立場に立てば、惑星の天球上での順行・逆行という見かけの動き(視運動)は、たんに内惑星は地球より速く動いていて、また外惑星は地球より遅く動いているので、地球は内惑星には追い越され、外惑星を追い越す、そのときの見かけの動きということで、天動説よりも簡単に説明できる。
ただし、地動説の直接的な最初の証拠は、公転の年周光行差の観測が1728年、自転のフーコーの振り子の実験が1851年であり、ニュートンが生きていたときにはまだ地動説の証拠はなかったことになる。
その後、太陽系の中心である太陽も、数多くある恒星のなかの平凡な一つにしか過ぎないということもわかってきた。太陽は数千億個の恒星の大集団である半径5万光年という円盤形(渦巻き型)の銀河系の中では、中心から2.8万光年という辺境の地にある平凡な恒星である。その銀河系そのものが、無数といってもいいほど数多くある銀河の中では平凡な銀河の一つでしかない。一見、われわれを中心に膨張しているように見える宇宙だが、じつは宇宙には「中心」はない。
われわれの宇宙観の変遷は、素朴な「地球が宇宙の中心である」という考えから、だんだんと地球を宇宙の片隅に追いやる歴史であった。こうした、われわれの地球(太陽系)が特別な存在でない、そもそも宇宙には特別な場所=「中心」がないという考えが宇宙原理である。
それに対して、人間こそがその宇宙を認識している。そして人間(生命)は、この宇宙が非常に微妙な物理定数(万有引力とか、光速度とか)のバランスがあったからこそ存在できた。こうした微妙なバランスが実現しているこの宇宙(他の物理定数のもとでの宇宙もあるかもしれない)ではじめて生命、すなわち人間もが誕生できた。こうした考え、つまり一度宇宙の片隅に追いやられた地球(人間)の復権を目指すものが人間原理である。人間原理については神戸大学を松田卓也氏のサイト(http://www.edu.kobe-u.ac.jp/fsci-astro/members/matsuda/review/ningengenri.html)を参照。
このページの参考になるサイト