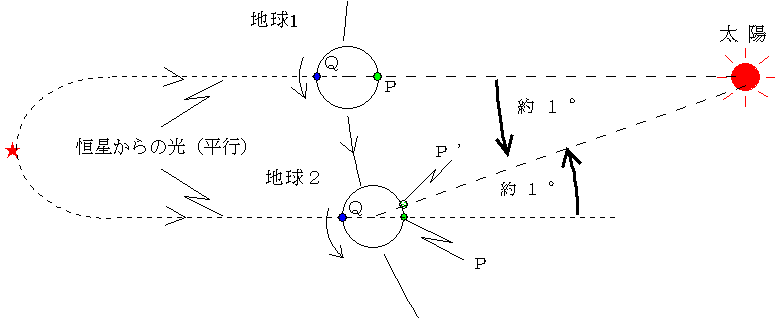
6. 地球の自転と公転の周期
地球は自転しながら、太陽のまわりを公転している。
a.自転周期
何を基準にして、自転周期を測るのかをきちんと決めておかなくてはならない。
a−1 恒星日
遠い恒星は見かけの位置を変えない(年周視差が観測されたとしてもごく小さい値である)ので、基準として適している。つまり、ある恒星が南中(真南に位置すること)から南中までの周期を1日とするのである。これを恒星日という。
1恒星日=23時間56分4秒
この周期はわれわれがふつう1日としている24時間より約4分短い。だから、ある恒星の南中時刻は1日で4分ずつ早くなる。1か月では2時間早くなり、半年後には12時間早くなる。つまり、真夜中に南中していた恒星が、真昼に南中することになる。真昼ということは実際は見えないということである。真夜中には別の恒星が南中することになる。そして、1年後に再びもとに戻る。こうして、季節によりよく見える恒星・星座が異なってくる。
a−2 太陽日
恒星日は日常生活では不便である。われわれは太陽の日周運動をもとにした時間で生活している。つまり、日の出とともに起きて活動を初め、太陽が南中するころに休憩し、日没後は休むという感じである。だから、太陽が南中してから再び南中するまでを1日とした方が都合がよい。これを太陽日という。
1太陽日=24時間
では、なぜ恒星日と太陽日では約4分のずれを生じるのだろう。下図(太陽系を北極の真上から見おろした図)のように、地球1の位置でP点では太陽が南中し、P点と反対側のQ点ではある恒星が南中している。この地球が自転しながら太陽のまわりを公転する。1日後(1恒星日後)に、Q点ではある恒星が再び南中する。このとき、遠い恒星からの光は太陽系程度の規模では平行であると考えている。だが、この位置ではP点ではまだ太陽は南中していない。P点で太陽が南中するためには、地球はもう少し回転しなくてはならない。こうして、1恒星日よりも1太陽日の方が長いことがわかる。
そして、地球1の位置から地球2の位置までの時間は1日、地球は太陽のまわりを1年で1周する、つまり、約360日で360°回転する。だから、地球1−太陽-地球2のなす角度は約1°となる。恒星日から太陽日(P点がP’点まで回転する)角度も、恒星からの光は平行と考えていいので、1°である。地球の自転は1日(24×60分=1440分)で1回転(360°)だから、1°回るには4分(=1440分÷360°)かかる。こうして、1太陽日の方が1恒星日よりも約4分長いことがわかる。
本当は下の図は、1恒星日後の地球の位置(地球2の位置)から、1太陽日までの間にもう少し地球は太陽のまわりを回転して、地球は地球3の位置に来ているはずである。しかし、図を描けばわかるように、本質的には変わらない。気になる人は作図して確かめてみよう。
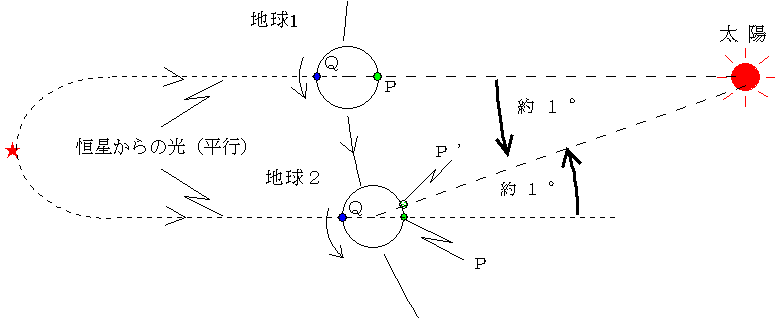
a−3 平均太陽
じつは、太陽が南中してから再び太陽が南中するまでの時間は一定ではない。これは地球が太陽のまわりを回る公転軌道が円でなくだ円であること、地球の自転軸が公転面に垂直でないために起こる。そこで、1年を天の赤道を平均して動く仮想的な太陽を考え(これは地球の軌道を円とし、自転軸が公転面に垂直としたことになる)、この平均太陽が南中してから南中するまでを1日、すなわち1日とする。
b. 公転周期
地球が太陽のまわりを1周するのに要する時間が公転周期である。つまり、地球から見て太陽がある恒星の位置に見えてから、再びもとの恒星の位置に戻るまでの時間、天球を使えば天球上のある一点から出発した太陽が西から東に動いて、出発点に戻るまでの時間である。この恒星を基準とした1年と1恒星年という。
1恒星年=365.2564日
しかし、われわれは1年と季節の巡りを一致させた方が良い。つまり、例えば春分から春分までの長さを1年とした方が都合がよい。ところが春分点は歳差のために、1年に50″(49.85″)というごくわずかの大きさだが東から西に移動する。天球上の太陽の動きは、西から東で春分点の移動の向きと逆である。つまり、春分から春分までの方が1恒星年より少し短いことになる。この長さを1太陽年とする。1年を365日とすると、地球が太陽のまわりを49.85″回転するのに要する時間(日)は、0.014094日。これだけ1太陽年の方が、1恒星年よりも短い。この数値では1太陽年は365.2424日になるが、もう少し正確な数値を用いると
1太陽年=365.2422日
となる。われわれが暦をつくるときのもととなる1年の長さは、この1太陽年の方である。