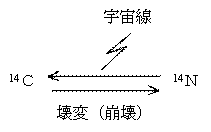
第13章 年代測定法(3)
| 目次 | |
| 2. | 年代測定法各論 |
| a.炭素14法 | |
| b.カリウム−アルゴン法 | |
| c.ウランー鉛法 | |
| 用語と補足説明 | |
| このページの参考になるサイト | |
下に挙げたた代表的な方法以外にも、最近では様々な元素を用いて、いろいろな方法で年代測定が行われている。
2.年代測定法各論
a.炭素14法(14C法)
空気中の炭素14(14C)は壊変(崩壊)するとチッ素14(14N)になる。しかし、14Nに宇宙線(宇宙からやってくる高エネルギー粒子)によって14Cになる(詳しくは宇宙線が大気を構成している原子と衝突して中性子をはじき出し、その中性子が14Nの原子核の陽子をはじき出して14Cとなる)。現在は、14Cが14Nになる速さと、14Nが14Cになる速さが同じ、つまり平衡状態になっている。
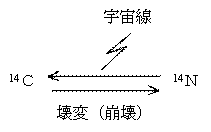
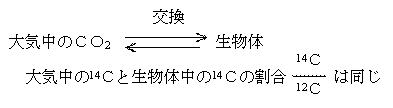
生物体のもとになるのは植物が光合成で作った有機物である。植物が生きている間は、大気中の二酸化炭素(CO2)を使うので、植物体の有機物も、それを食べる動物体の有機物も、その中の14Cの量(割合)は大気の中の14Cの割合と同じである。ところが生物が死んで地中に埋まってしまうと(宇宙線を浴びなくなってしまうと)、14Cだけが一方的に減っていくことになる。ここで、昔も14Cと14Nが現在と同じ平衡状態にあったとすれば、生物の遺体中の14Cもその生物が生きている間は現在と同じであったのが、死んでからは半減期5730年で減っていくことになる。
つまり生物の遺体中の14Cが現在の1/2であればその生物は5730年前に、1/4であれば11460年前に、1/8であれば17190年前に、さらに1/16であれば22920年前に死んだことになる。実際は誤差があるので、当然±の範囲を見積もらなくてはならない。計算式は下を参照。
炭素14法(14C法)は、木片などに対してよく使われる。人類遺跡のたき火のあとなどもよい。近いところでは古文書などに対しても使われることがある。
炭素14法(14C法)の最大のメリットは、初期値の推定がいらない(現在の大気中の14Cの存在比を初期値としてよい)ということである。逆に最大のデメリットとしては、地史を研究するには14Cの半減期が短すぎることである。半減期が5730年では、せいぜい十数万年前までという時間スケールをはかるのには使えるが、数百万年、数千万年という時間スケールでは使えない。
もう一つの不安は、前提である過去も14Cの崩壊と14Nからの生成が現在と同じ平衡状態であったとということである。しかしこれは、逆にいえばせいぜい数万年前までなら大丈夫であろう。
炭素14法(14C法)は、生物が死んでから現在までの年数を測定することになる。
カリウム40(40K)は半減期12.5億年で壊変(崩壊)して、アルゴン40(40Ar)に変わる。娘元素である40Arは気体であることが、この方法のメリットでもあり、デメリットにもなる。
気体であるは40Arは、岩石が熱せられると逸脱してしまう。つまり0(ゼロ)となる。つまり初期値を0(ゼロ)としてよい。そして、岩石が冷えてからは逸脱できずに岩石の中にたまっていく。岩石中にある40Arは岩石が冷えたあとでたまってきたものである
岩石中にたまった40Arは岩石を熱すると出てくるので、それを集めて測定すればよい。この現在の値をさかのぼり、Arが0になるまでの年代を求めることになる。ただし実際の計算は少し複雑である。
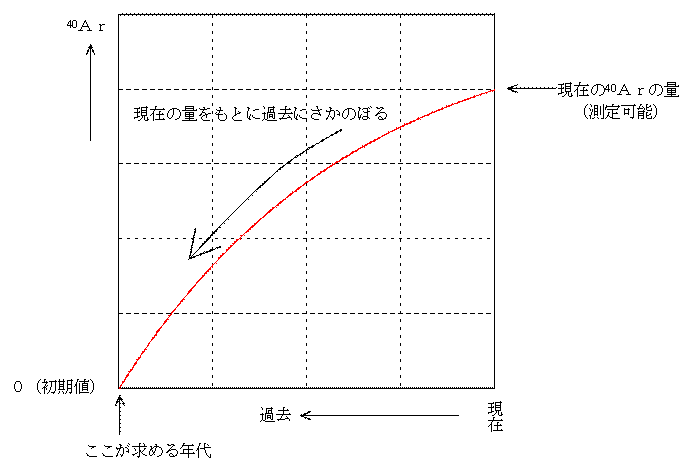
K−Ar法のメリットは、なんといってもカリウム(K)は岩石中の含有量が多いことである。だから半減期が12.5億年と少し長めではあるが、数千万年前(場合によっては数百万年前)から数十億年前という幅広い年代を測定できる。また娘元素の40Arが気体なので、試料を熱するだけで40Arを集めることできる。つまり、測定が非常に容易である。
しかし娘元素である40Arが気体であることは、岩石が冷えた後も岩石から逸脱する心配もある。実際、U−Pb法などと併用すると若い年代を出すことが多い。ただし、この性質を積極的に使えば、熱による変成年代を求めることができる可能性もある。U−Pb法では、マグマが冷え固まって火山岩になってからの年代を求めることになるが、K−Ar法は火山岩になったあとに変成作用(岩石が融けない)を受けたとすると、その変成年代を求めることができるのである。
K−Ar法は、岩石が最後の加熱を受けてからの年代を求めることになる。
ウラン−鉛法(U−Pb法)では、初期値を現在値としてよい炭素14法や、初期値を0としてよいカリウム−アルゴン法と異なり、工夫が必要である。
もし同じ岩石の中で、ウラン(U)の濃度が高くなった部分(鉱物)と、低くなった部分(鉱物)ができたとする。すると、それ以後はUの濃度の高くなったところからは娘元素であるPbがたくさんでき、低くなったところではあまりPbができないことになる。娘元素であるPbがたくさん集まったところのPbの量から過去にさかのぼり(図の赤線)、Pbがあまり集まらなかったところのPbの量から過去にさかのぼると(図の青線)、どこかで交わるはずである。この交わったところがウラン濃度に差ができたときである。
Uの濃度の差はマグマが冷えて固まるときにできる。イオン半径が大きいウランは液体の中に入りやすいので、晶出が早い鉱物の中にはあまり入らず、晶出が遅い鉱物の中に集まりやすい。そこで、火山岩の中では自然とUの濃度の高い鉱物と低い鉱物ができる。だから、同じ岩石の中の晶出の早い鉱物中の娘元素のPbの量、晶出の遅い鉱物の中のPbの量を測定するとPbの量に差があるはずである。これを過去にさかのぼって、この交点、マグマが冷えて固まったとき、すなわち火山岩ができた年代を求めることができる。計算式は下を参照。
火成岩でも深成岩の場合は冷えて固まるまでに長い年月がかかるので、どの時期にUの濃度に差ができたかがよくわからないので、この方法は使えない。逆に同じ岩石でなくても、同じ時期の形成されたことがはっきりわかっているものであればU−Pb法を適用できる。たとえば鉛鉱床は化学的な性質からできるときにUを取り込まない。だから鉛鉱床中の娘元素であるPbは、鉛鉱床ができたときにはじめから含まれていたものであり、その後は増えていない。だから鉛鉱床中の娘元素であるPbの量を初期値として、まわりの岩石中のPbの量をさかのぼればよい。
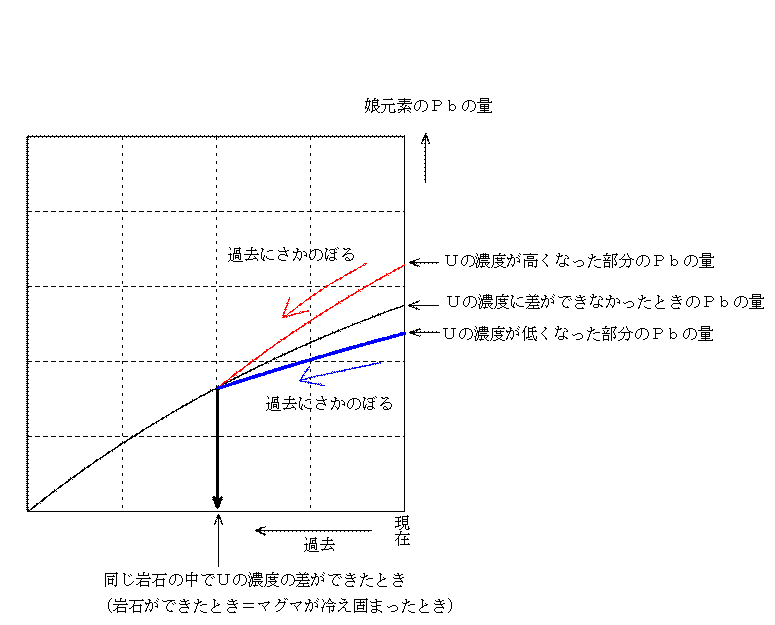
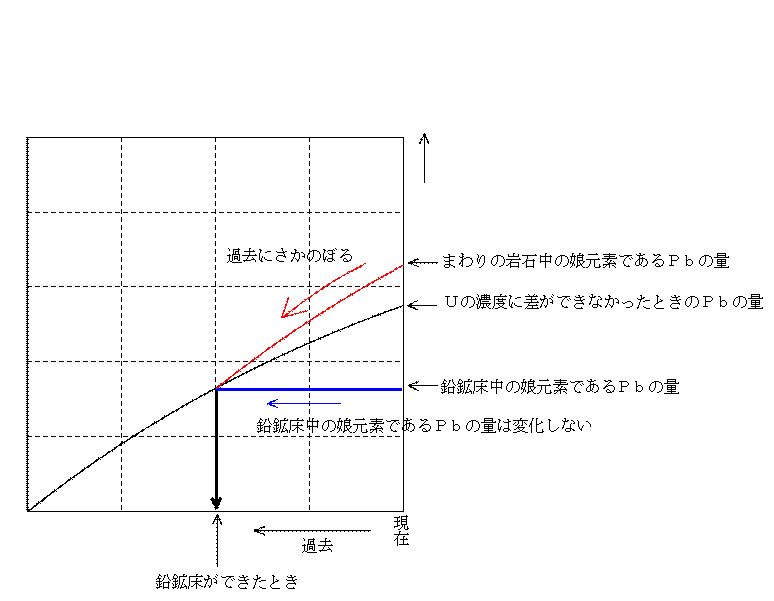
U−Pb法は、同じ時代にできた岩石のなかでウランの濃度の差ができた(濃縮した部分と薄まった部分ができた)ときからの年代をはかること、つまりマグマが冷えて岩石になってからの年代をはかることになる。だからUの濃度が高くなったところと低くなったところの両方のサンプルが手に入ること、マグマの固結が比較的速く行われたことが必要である。こうした意味で、火山岩はUーPb法に適している。もちろん、その後融けては意味がない(リセットされる)。
U−Pb法は、親元素も娘元素も固体であるので、逸脱はあまりないのでK−Ar法のような心配はない。また、半減期(壊変定数)も比較的正確に求まっている。だが、その半減期が長いので、あまり短い年代測定には向いていない。またUの含有量が一般には少ないという問題がある。火成岩の中ではマグマの分化の最後の方に出てくるフェルシック(珪長質)の岩石に多く含まれ、マフィック(苦鉄質)のものにはあまり含まれていない。
炭素14(14C):安定同位体(放射能を持っていない同位体)である炭素12(12C)に対する割合。12Cは原子核に陽子6個、中性子6個、原子核のまわりに電子が6個というものである。一方14Cは中性子の数だけが12Cより2個多い8個であり、12Cよりも7/6(=14/12)だけ重い。ふつうは14Cの量は12Cに対する割合で表す。
宇宙線:大部分(87%)は陽子、残りの大部分(全体の12%)はヘリウムの原子核(アルファ粒子)である。これが高速で地球に飛び込み大気の分子と衝突する。太陽も宇宙線の発生源の一つではあるが、太陽だけでは説明できない。つまり、宇宙線の発生源についてはよくわかっていない。
炭素14法(14C法)の計算:現在の親元素の数がわかるので、の(2)式を適用して、その生物が死んだのが何年前(t年前)かを求める。

カリウムーアルゴン法(40K−40Ar法)の計算:40Kは壊変(崩壊)すると、12%が40Arに、残りの88%が40Ca(カルシウム40)になる。このうち40Caは元々たくさんあるので、40Kが壊変してできたものと区別できない。だから、年代測定に用いられるのは40K→40Arの方だけである。しかし、実際に計算するときには、40Arと40Caの分岐を考える必要があるので、娘元素に適用する(4)式をそのまま使うことができず、もう少し複雑になる。
ウラン−鉛法(U−Pb法)の計算:238U→206Pbの壊変定数をλ8(ラムダ8)、238Uの娘元素である206Pbの初期値を(206Pb)0、235U→207Pbの壊変定数をλ5、235Uの娘元素である207Pbの初期値を(207Pb)0とする。
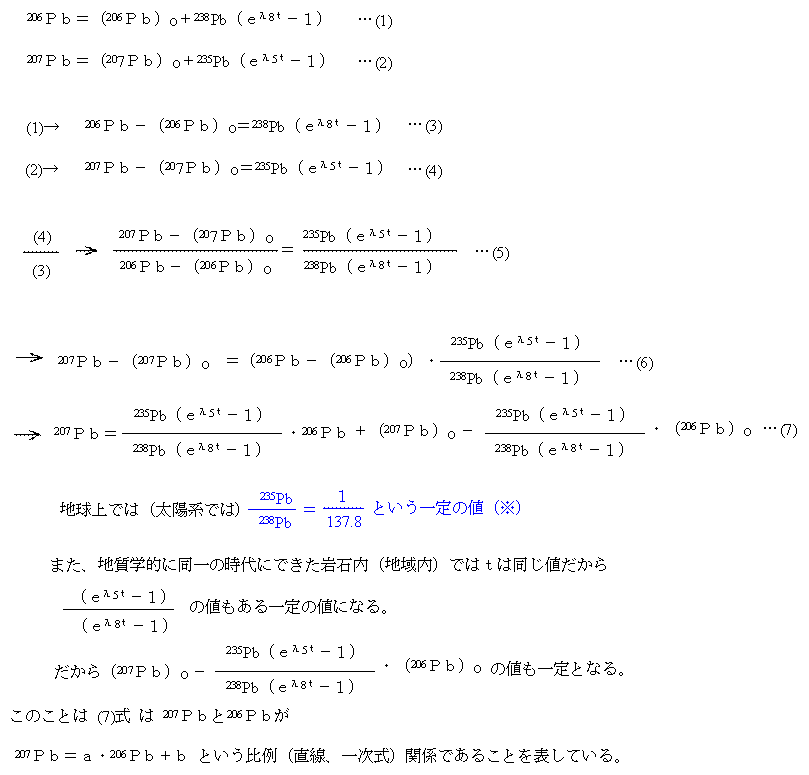
つまり同じ地質時代にできた207Pb、206Pbを数多く測定すると、そのサンプルのtは一定なので、その値は同じ直線の上に乗るはずである。この直線をアイソクロンという。例えば、はじめA、B、Cという207Pb、206Pbの値であったものは、t1年後にはその207Pb、206Pbの量はA1、B1、C1に、t2年後にはA2、B2、C2になっている。実際に測定されるのはA1、B1、C1という値や、A2、B2、C2という値である。A1、B1、C1を結んだ直線(緑色)の傾きから、t1という年代を、A2、B2、C2を結んだ直線(赤色)からt2という年代を求めることができるのである。
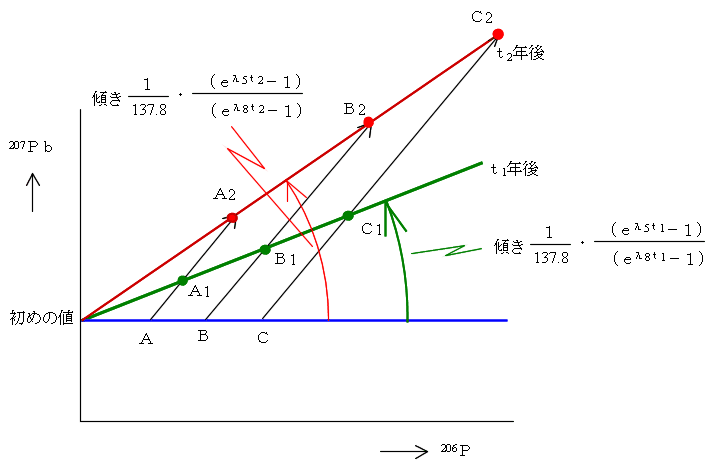
なお、実際には207Pb、206Pbの量を直接はかることはなく、安定な同位体204Pbを基準とした相対比 と
と をはかる。
をはかる。
235Uと238Uの比:地球のどのウラン(U)ばかりではなく、手に入る太陽系のサンプル中のどのUも、半減期が異なる235U:238Uは一定で1:137.8である。このことは、太陽系の物質をつくる元素は、単一の超新星爆発であるか、あるいは複数の超新星爆発であったとしても同じころに爆発したものであることを示す。この件についてはこちらも参照。超新星についてはこちらも参照。
名古屋大学年代測定総合研究センター:http://www.nendai.nagoya-u.ac.jp/index.html