









2007年7月24日〜26日、北アルプス北部の
このコースはちょうど25年前に行ったことがあります。1日の行程が長いコースです。25年前はまだ小さかった子供たちを連れて行ったので大変でしたが、今回は自分の体力が落ちているのでまた大変でした。今回はレンズ3.5本(12-60mm(標準)、50mmマクロ、50-200mmに1.4倍テレコンバーター)を持って行きました。その重量のため、三脚とバーナーの持参はあきらめました。
(1) 1日目 (2) 2日目 (3) 3日目 (4) ライチョウ (5) 高山植物
(1) 1日目(7月24日)
前日の23日の10時半ころ自宅を出発。中央道を使って豊科ICで降り、猿倉へ向かいます。白馬に近づいたあたりから、断続的に強い雨になりました。猿倉の登山者用駐車場に車を入れます。15時半くらいでした。車外に椅子を持ち出してのんびりしようと思っていたのですが、断続的な雨が続くので車内で夕食を済ませ、早めに寝ることにしました。
24日はまだ薄暗い4時半ころに出発。幸い雨はあがっていますが、上部がガスっています。白馬尻までは緩い上り坂です。白馬尻は5時40分。白馬尻小屋前はこれから大雪渓を登ろうとする大勢の登山者たちがいます。中には最近では珍しい、高校(?)女子の山岳部の団体も。
大雪渓の末端は6時。ここで簡易アイゼンをつけます。アイゼンを持っていない人は猿倉山荘などでも手に入ります(レンタルもあり)。雪渓は滑りさえしなければ(アイゼンをつけていれば)、ふつうの登山道よりも歩きやすい。ただ、ガスっているとルートがわかりにくいかもしれません(この大雪渓は赤い紅殻でルートがしっかり示されています)。それよりも四六時中の落石が、ガスっていると音だけが聞こえるので少し怖いかもしれません(実際にも危ない)。この日はいちおう視界があったので、落石の状態を眼で確認することが出来ました。それでもときどきガスに包まれます。このときは少しムアーッとした感じになります。
大雪渓を登り切ったのは7時55分。ここからいったんふつうの登山路になります。このあたりからは高山植物が満開のお花畑が続きます。まもなく小雪渓。ここはトラバース(横切り)します。下を見ると怖いくらい。まだこれからも少し雪渓が残っているところを登るところがありますが、ここまで来れば頂上は近い。ガスの中から白馬岳頂上宿舎が突然見えたのが10時10分。ここのレストラン(アルペンプラザ)では2,300円のディナー、1,300円のモーニングセットを注文することが出来ます。う〜ん、山小屋も変わりました。
疲れていたので、ここに泊まろうかとも思いましたが、少しでも頂上に近い白馬山荘をめざすことにしました。稜線は風が強い。白馬山荘には10時半ころ到着。受付が11時からということで、その間にテルモスに入れておいたお湯で飲み物をつくり、パンの昼食としました。11時受付。1泊夕食のみで8,000円(朝食をつけると9,000円)でした。割り当てられた部屋は8畳くらいでしょうか、最終的には6人だったので1人布団1枚分以上ということになります。この山小屋にも立派なレストラン(スカイプラザ白馬)があります。ここで恒例Tシャツを買って生ビール(760円)を頼みました。
部屋に戻り少し昼寝をしたあと、頂上まで散歩に行きました。登りはおもに50mm(35mmフィルムカメラ換算100mm)F2マクロ、下りは50-200mm(35mmフィルムカメラ換算100-400mm)F2.8-3.5というレンズをつけて歩きました。だが、風がものすごいので思うように写真を撮ることができません。白馬岳は飛騨側が比較的傾斜が緩く、信濃側が崖になっている非対称のおもしろい地形なのですが、これもガスのためによくわかりません。でもたくさんの高山植物を楽しめたし、おまけに下りではガスの中からライチョウ(雷鳥)が登場してくれました。
山荘の夕食はこのようなものでした。朝・昼と粗食だったのでたくさん食べてしまいました。
写真はクリックすると拡大します。戻るときはブラウザの“戻るボタン”をご利用ください。
 |
 |
 |
 |
 |
| 朝の猿倉山荘。 | 白馬尻への道。 | 大雪渓の末端。すでに3名の登山者が先行しています。 | 大雪渓の上端が見えてきました。赤い紅殻でルートが示されています。 | 登ってきた大雪渓を振り返ります。遠くに戸隠連峰が見えています。 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 大雪渓を登り切りました。大勢の登山者が登ってきます。雪渓の上部はこのように落石が散在しています。 | 小雪渓をトラバースしようとしている登山者。途中から下を見降ろすとこんな感じ。 | ガスの中から突然村営頂上宿舎が見え出しました。 | 白馬山荘のレストラン白馬の内部。ピアノの生演奏もありました。 | 白馬岳山頂(2932.2m)。ガスで何も見えません。 |
1日目 2日目 3日目 ライチョウ 高山植物 山行目次へ戻る home
(2) 2日目(7月25日)
この日は雪倉岳を越えて朝日岳までです。行程が長いので、朝食は自分で持ってきたパンで済ませて、4時半に小屋を出ました。まだかなり暗いので、ライトをつけて登り始めます。この日もガスと猛烈な風です。寒いかと思って、ウールの長袖、さらにフリースも着て、その上からレインウェアといういでたちです。でも、レインウェアで風さえ防いでいれば、そして歩いていればそれほど寒くはありません。小屋から頂上まで10分ほどです。でも起き抜けの登りはきつい。頂上でまずフリースを脱ぎました。
展望がない頂上に長居をしても仕方ないので、白馬大池との分岐である三国境をめざして出発。三国境で長袖も脱ぎました。ガスと強風は相変わらずですが、たくさんの高山植物に慰められながら進みます。眼前に鉢が岳の大きな山容が見えると鉱山道経由で蓮華温泉に降りる道と分かれます。鉢が岳へは踏み跡がついているようですが、これから行く雪倉岳へのメインルートは何回か雪渓をトラバースして鉢ガ岳を巻きます。雪渓は一部凍結しているの注意が必要です。ただ、巻き道側は風下側になるので、風が弱くて助かりました。
雪倉の避難小屋は7時50分。トイレもついた立派な小屋で中もきれいでした。中で15分ほど休みます。雪倉岳への登りの途中でライチョウの雄が登場しました。あわててレンズを50-200mmに付け替えます。しばらくライチョウと遊んでから、また登り再開。雪倉岳の頂上(2,610.9m)は8時55分、50分ほどの登りでした。晴れていれば大展望のはずですが、まったく何も見えません。かなり降りて樹林帯に入り、またかなり行って疲れたころに水場がありました。とてもおいしい。ここで昼食とします。
その後湿地となり木道が現れ始めます。このあたりは小桜ヶ原というらしいです。たしかにたくさんの(ハクサン)コザクラ、さらにはミズバショウも咲いていました。
小さな雪渓の途中で、朝日岳への登山路と、朝日小屋への巻き道(水平道)の分岐があります。25年前、水平道という名に惹かれてこちらを通りましたが、小さなアップ・ダウンが多くて大変でした。今回は朝日岳への道を選びます。11時50分に登り開始。最初は樹林帯の中の急登です。樹林帯を抜け、傾斜が緩くなったところで今度は子連れのメスのライチョウが登場しました。またライチョウとしばらく遊びます。雪渓の上を歩いている子供が可愛い。ただ、ガスが濃いのでせっかくの望遠レンズですが、くっきりという具合には撮影できません。
朝日岳の頂上付近も植生保護のために木道になっています。蓮華温泉や
下りは木道、ふつうの登山路、雪渓という感じです。水平道と合流したのが14時45分。ここからほんの小さな登りですが、疲れている身にはつらい登りを登り切ると、ガスの中一瞬朝日小屋が見えました。やっとただりついたという感じです。小屋到着は15時だったので、この日は10時間の行程でした。
朝日小屋は予約が原則だそうです。最近は予約が必要な山小屋が多くなってきたようです。私は昔のイメージでふらっと来てしまいました。もちろん泊めてもらえます(1泊夕食のみ8,000円)。20畳くらいの大きな部屋に、最終的には12人程度でしたのでゆったりです。ただ、次の日はすでに200人の予約が入っていて、予約なしの人ための部屋は一つしかないとのことでした。予約が必要になった背景には、小屋利用者の意識の変化(とくに女性から隣に知らない男の人が寝ているところでは寝られないというクレームが多いそうです)、また豪華な食事(客もそれを求める、典型的な例が白馬山頂の2軒の山小屋)を用意するようになってきて、その食材の準備のためでもあるようです。朝日小屋は25年前とはまったく違うほど立派できれいな建物になっていました。トイレなどは水洗でした。
写真はクリックすると拡大します。戻るときはブラウザの“戻るボタン”をご利用ください。
 |
 |
 |
 |
 |
| まだ暗い中、白馬山荘を出発しました。 | 白馬岳の頂上。 | 三国境の指導標。 | 二重山稜の窪地にはまだ雪がたくさん残っています。 | 鉢ガ岳はガスに包まれています。雪渓にルートが示されています。 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 鉢が岳の巻き道からの光景。 | 雪倉の避難小屋が見えてきました。 | 雪倉岳の頂上です。何も見えません。 | 小桜ヶ原の木道とミズバショウ。 | 朝日岳の頂上。 |
1日目 2日目 3日目 ライチョウ 高山植物 山行目次へ戻る home
(3) 3日目(7月26日)
この日は蓮華温泉に下ります。この行程も長いので朝食を簡単なパンで済ませて、5時に小屋を出発しました。この日もガスと強風です。朝日岳へ登りにある雪渓の端の凍っているところでスリップして、お尻に雪渓上のルートを示す紅殻をつけてしまいました。この日は木道でもスリップして転んでしまいました。年をとるとスリップが事故につながります。
頂上は6時5分。展望がないのでそのまま通過します。途中の風の弱いところで朝食をとっている東大宇宙工学研の若い院生グループを抜かします。彼等とは蓮華温泉までつかず離れずの状態でした。蓮華温泉と栂海新道の分岐が6時40分。五輪尾根に降りるまで何回か雪渓を横切ったり、また小さな沢を徒渉したりします。一つの雪渓で東大グループが雪渓の端を踏み抜いてくれたので、後続は危険箇所を回避できました。
木道が現れ、ミズバショウが咲く一つの雪渓の脇においしい水がありました。あとはもう下りだと思い、ザックの中に入れてい置いた50mmのマクロレンズと、50-200mmの望遠ズームを取り出して、マクロはウェストポーチに、望遠はカメラケースをたすきがけにして外に出すことにしました。手始めに、あとから降りてくる東大院生グループの写真を望遠で撮りました。
さらに下り小さな雪渓を横切るとまた小さな湿原と木道の道になります。大勢の登山者(ツアー?)が登ってきました。このコースを上りに使うのは結構大変だと思います。この湿原は休憩の場所にはもってこいです。花もたくさんあるので、マクロレンズで撮影してみました。この湿原を越えるとカモシカ坂の急降下。しばらくは我慢して歩いていましたが、疲れてきたので再びマクロと望遠レンズをザックの中にしまいました。
ようやく白高知沢に降り着いたのが10時40分。昼食&大休止とします。水が冷たくておいしい。顔を洗ったり、水を入れ替えたりしました。引き上げようとするころに東大グループがやってきました。沢の徒渉は、少し上流に行ったところに仮設の橋があるのでそれを利用します。渡るとまた一つ尾根を越えるための登りです。つらい。次の瀬戸川橋は12時10分。ここは大昔もっこの渡しがあったはずです。いまは立派な、でも足場は簀の子状の橋が架けられています。
橋を越えるとまた樹林帯の急登。木道が出てくると傾斜は緩くなりますが、兵馬ノ平、アヤメ平という小湿原を挟んで最後の蓮華温泉まで登りが続きます。疲れている身にはつらい。兵馬ノ平(13時5分)で少し休んで、蓮華温泉に着いたのが14時10分。もう少し早く着いていたら、お風呂に入っても14時20分のバスに乗って、この日のうちに猿倉に駐めておいた車を回収し、帰宅できたのですが。次のバスは16時過ぎなので、ここに泊まることにしました(1泊夕食・朝食付き9,000円)。とくに予約の必要はないみたいです。泊まると決めてしまえばのんびりなので、温泉(内湯)に入ったり、ビール(350mLが450円)を飲んだり、ぼーっと部屋から外を見ていたり、相部屋の人と話したりして過ごします。
部屋は6畳程度に3人でした。夕食はこんな感じです。
翌日(27日)は、朝食前に野天風呂めぐり(4つの湯を全湯制覇)しました。朝一番のバス(7時20分)に乗ると、JR大糸線
写真はクリックすると拡大します。戻るときはブラウザの“戻るボタン”をご利用ください。
 |
 |
 |
 |
 |
| 蓮華温泉と栂海新道の分岐。 | 雪渓の下に池塘群が見えます。 | まだガスっていますが、少し風景が見え出しました。 | オオバギボシの向こうに小さな湿原が見えます。 | 花園三角点の上の湿原を登ってくる登山者。 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 白高知沢の流れ。 | 仮設の橋。 | 瀬戸川橋。 | 兵馬ノ平。 | 野天風呂の一つ、仙気ノ湯。 |
1日目 2日目 3日目 ライチョウ 高山植物 山行目次へ戻る home
(4) ライチョウ(雷鳥)
おまけのイワヒバリはこちら。
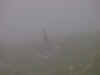 |
 |
 |
 |
 |
| 7月24日、白馬岳頂上近くに現れたライチョウ。 | 7月25日、雪倉岳の登りの途中で出会った雄のライチョウ。 | 立派な雄のライチョウでした。 | だんだん霧の中へと消えていきます。 | 雪倉岳への登り途中、メスのライチョウです。 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 雛が2羽います。 | 再びメス。 | 雪渓の上を歩く雛。 | 枯れ草の上を歩く雛。 | やっとお母さんと合流できました。 |
1日目 2日目 3日目 ライチョウ 高山植物 山行目次へ戻る home
(5) 高山植物(名前には自信がありません)
写真はクリックすると拡大します。戻るときはブラウザの“戻るボタン”をご利用ください。
a.24日(白馬尻〜白馬岳)
 |
 |
 |
 |
 |
| キヌガサソウ | ミヤマキンポウゲ | ハクサンフウロ | ミヤマタンポポ | クルマユリ |
 |
 |
 |
 |
 |
| オタカラコウ | イワオウギやクルマユリの群落 | ハクサンイチゲ | シナノキンバイ | イワカガミ |
 |
 |
 |
 |
 |
| ミヤマオダマキ | 氏名不詳 | タカネシオガマ | チシマギキョウの群落 | コマクサ |
 |
 |
 |
 |
 |
| タカネツメクサ | ミヤマクワガタ | ヨツバシオガマ | ウルップソウ | タカネヤハズハハコ |
b.25日(白馬岳〜雪倉岳〜朝日岳)
 |
 |
 |
 |
 |
| イワベンケイ | ハクサンイチゲ | コマクサ | チシマギキョウ(花に白い毛がある) | イブキジャコウソウ。大きさはこちらを参照(レンズキャップは72mm径)。 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ハクサンシャクナゲ | イワオウギ | ミヤマムラサキ | アオノツガザクラ | コケモモ |
 |
 |
 |
 |
 |
| タカネバラ | タカネスミレ | ハクサンシャジン | チングルマの雌しべ(花はこちら) | ミヤマダイモンジソウ |
 |
 |
 |
 |
 |
| ニッコウキスゲ | ミヤマダイコンソウ | ゴゼンタチバナ | ミヤマアズマギク | ミネウスユキソウの群落 |
 |
 |
 |
 |
 |
| シラネアオイ | オタカラコウ | ミヤマカラマツ | タカネマツムシソウ(後ろにミネウスユキソウ) | ヨツバシオガマ |
 |
 |
 |
 |
 |
| ミズバショウ | リュウキンカ | ハクサンコザクラ | ショウジョウバカマ | ハクサンチドリ |
c.7月26日(朝日岳〜蓮華温泉)
 |
 |
 |
 |
 |
| ウツボグサ | ソバナ | シロウマアサツキ | ハクサンコザクラ | ウサギギク |
 |
 |
 |
 |
 |
| シラネアオイ | 氏名不詳 | シモツケソウ | ナナカマド | タテヤマリンドウ(横顔はこちら) |
 |
 |
 |
 |
 |
| ミヤマアズマギク | イワイチョウ | ヒオウギアヤメ | カライトソウ | イワブクロ |
2008年7月記
1日目 2日目 3日目 ライチョウ 高山植物 山行目次へ戻る home