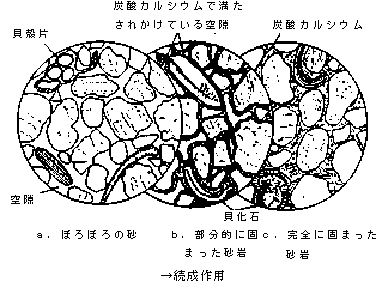
第10章 堆積岩と地層(3)
2.堆積岩
a.続成作用
堆積物が堆積岩となる作用を続成作用という。具体的には、さらに上に堆積した堆積物による圧力で、押しつぶされ(圧密)、鉱物同士がくっつき(膠着(こうちゃく))、さらには新しい鉱物ができることもある(再結晶)。変成作用も参照。
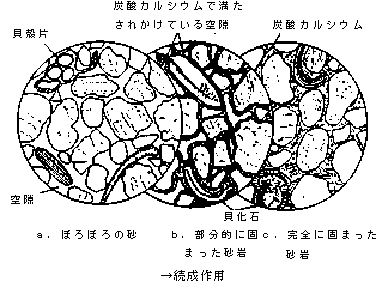
堆積岩の多くは、流水により運ばれてきた砕屑物(さいせつぶつ、風化・浸食により細かくされた岩石・鉱物の粒子)が水底で堆積してできるので、水成岩ともいわれる。堆積岩は地層を形成する岩石である。
b.堆積岩の分類
堆積岩は起源や粒子の大きさで分類する。石灰岩やチャートには、生物の遺骸が集積してできたものと、化学的に沈殿してできたものがある。
b−1 砕屑岩(さいせつがん、風化・浸食・運搬による堆積物からできたもの)
| もとになる堆積物 | 粒子の大きさ | 名称 | |
| れき(礫) | 2mm以上 | れき岩(礫岩)、とくに角張ったれきだと角れき岩 | |
| 砂 | 1/16mm〜2mm | 砂岩 | |
| シルト | 1/256mm〜1/16mm | シルト岩 | 泥岩・頁岩(けつがん)・粘板岩 |
| 泥(粘土) | 1/256mm以下 | 泥岩(粘土岩) | |
 |
 |
| れき岩。1円硬貨の直径は2cm。 | 砂岩 |
 |
 |
 |
| 泥岩 | 頁岩(けつがん)。泥岩よりも薄く平行に割れやすい。 | 粘板岩。頁岩よりさらに薄く平行に割れやすくなっている。 |
b−2 火山砕屑岩(火山性の堆積物からできたもの)
おもに火山灰が集積してできた岩石を凝灰岩(ぎょうかいがん)、火山れきなどが多く混じっていれば火山角れき岩という。詳しくを下を参照。また、火山灰、火山れきなどの火山砕屑物についてはこちらを参照。
 |
| 凝灰岩(ぎょうかいがん) |
b−3 化学岩(化学的に沈殿したものからできたもの)
| もとになる堆積物 | おもな化学組成 | 名称 |
| 炭酸塩沈殿物 | CaCO3 | 石灰岩 |
| ケイ酸塩沈殿物 | SiO2 | チャート |
| 蒸発残留物 | NaCl | 岩塩 |
| CaSO4・2H2O | 石膏(せっこう) |
b−4 生物岩(生物の遺骸が堆積してできたもの)
| もとになる生物 | 名称 | |
| 石灰質の生物遺骸 | サンゴ・紡錘虫(フズリナなど) | 石灰岩 |
| ケイ質の生物遺骸 | 放散虫 | チャート |
| 植物 | 石炭 |
※ 石灰岩やチャートには化学的にできたものと生物の遺骸からできたものがある。
 |
 |
| 石灰岩 | チャート |
火山砕屑岩の分類:火山砕屑岩の分類法には何種類かあるが、「ネットで百科」では、火山岩塊・火山弾、火山れき、火山灰の混じり具合に応じて下のようにしている。図では、三角形の中の位置で3つの混じり具合を示している。上に行けば行くほど火山岩塊・火山弾の割合が多く、下左に近づけば火山れきの割合が多く、下右に近づけば火山灰の割合が多くなる。
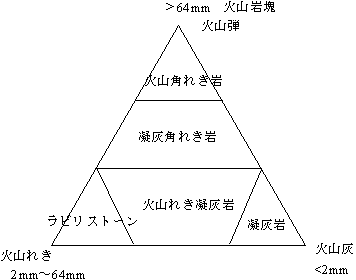
凝灰岩のうち、とくに軽石を多く含むものを軽石凝灰岩、スコリアを多く含むものをスコリア凝灰岩という。建築材としてよく使われる大谷石(おおやいし)は、火山灰(流紋岩質)が海底に堆積してできた凝灰岩であり、薄い緑色をしている。
また、火砕流などが高温のまま急速に大量に堆積すると、火山灰など粒子が自分の重みでつぶれて互いにくっつき、溶岩のように緻密に固まることがある。こうしてできた凝灰岩が溶結凝灰岩である。北海道の層雲峡や九州の高千穂峡は、溶結凝灰岩が侵食されてできたものである。