
図1-15 畜産物1kgを生産に要する穀物量(http://166.119.78.61/j/study/syoku_mirai/pdf/data2-1.pdf)
現在の地球の人口は約70億人、しかもまだどんどん増え続けている。問題は、こうした人口を、この有限な地球が養っていけるかである。
(2) 食糧問題
飢えた人がいる一方で、飽食の人がいる。今日、食糧は一応十分に生産されているはずなのに、このような現実が生じるということは、まさに食糧が公平に分配されていないことを示す。
これは直接食糧として摂取されるエネルギーだけが不公平なのではない。食生活にも問題がある。必須アミノ酸を家畜の肉として摂らざるを得ないとしても、おもに豚肉を食べるのか、牛肉を食べるのかで意味が異なる。畜産物1kgを生産するのに必要な穀物量の見積もりは下を参照。

図1-15 畜産物1kgを生産に要する穀物量(http://166.119.78.61/j/study/syoku_mirai/pdf/data2-1.pdf)
つまり、効率の悪い牛肉を食べるということは、豚肉を食べることよりも穀物を消費していることにもなる。牛肉をふんだんに食べるということは、穀物の価格をつり上げ、貧しい人たちをさらに飢餓に追い込むこということになる。ふんだんに牛肉を食べている自分を省みることなく、日本のクジラ食を「感情的に」批判している、欧米の一部の環境保護団体には、「犬を食べることを野蛮という方が野蛮」という言葉を贈っておこう(1・2の(2)e参照)。
しかし欧米ばかりでなく、日本や中国などのように、従来あまり牛肉を消費しなかった国も、経済的に豊かになってくると牛肉の消費がどんどん増えるという現実もある。
b 近代農業の問題
1・2の(1)でも書いたように、近代農業(先進国の農業)は、生産される穀物のエネルギー以上のエネルギー(化学肥料、農薬、あるいは機械力)を投入している。だがしかし、化学肥料だけに頼ればそのうち土地は疲弊していく。また農薬は環境汚染、あるいは食糧そのものの汚染を招きかねない。重いトラクターなどの使用は土を固めてしまう。
消費者の立場に立てば、農業に対するこのような多大な投資は、農作物の価格が高くなってしまうということである。
また、発展途上国の貧しい農民にとっては、このような投資は無理である。実際、発展途上国(多くは熱帯にある)の農業のための新しい穀物の品種の開発・普及(いわゆる「緑の革命」)は、その品種が近代農業を前提とする以上、効果をあげないか、あげるとすると化学肥料・農薬を購入できる富農に限られる。つまり、それができない貧農との格差がますます増大するという社会問題も生じる。
c 塩害
乾燥地で灌漑を施すと地下水位が上がり、そのうち毛管現象で地下水が地表にまで届くようになる。地下水にはごくわずかではあるが、塩分が溶け込んでいる。その地下水が地表で蒸発するときに、地表に塩分(塩化ナトリウム(食塩)、硫酸ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウムなど)を残し、それが集積する。
古代のメソポタミアの畑のコムギの単位面積当たりの収穫量は、現代のカナダ並みだったという。それが、だんだん灌漑設備が整うにつれて塩害がひどくなり、コムギの単位面積当たりの収穫量は1/2、1/3と落ちていった。メソポタミア文明衰退の一因である。
現代でもこれを解決するのは難しい。アメリカやエジプトなどの畑が悩んでいる。
この点、水田は毎年土壌を洗い流すために塩害が起こらないシステムなので、日本ではこれまでこの問題は深刻にはならなかった。
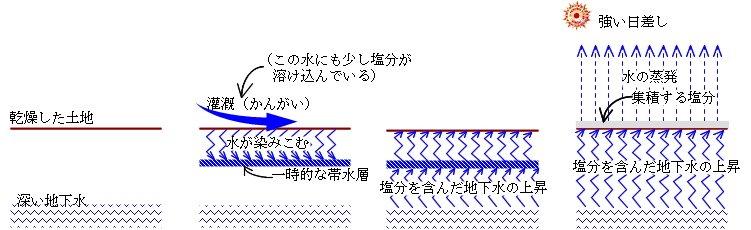
図1-13 塩害のメカニズム

図1-14 塩害が進み真っ白になった西オーストラリアの畑(2002年12月)
http://www.smh.com.au/articles/2002/12/11/1039379883655.html
d 砂漠化
年々進行する砂漠化により、耕地面積は圧迫されている。砂漠化については5・6参照。
e 海の生産力
1・2の(1)や(2)のaで書いたように、ヒトはどうしても必須アミノ酸を動物の肉という形で摂らなくてはならない。当然、家畜を育てるために穀物が消費されてしまうというなら、魚を食べるようにしたらいいのではないかと考えるだろう。
だが、じつは海の生産力は非常に低い。これは現在すでに、日本で消費する分だけでも、世界中の海から魚類を集めているということを考えればわかると思う。
海の中で湧昇という、深海から海水が昇ってくる場所、つまりそれによって巻き上げられた有機物によってプランクトンがたくさん生育できる場所はたしかに生産力が高い。しかし、その場所は非常に限られている。
次に生産力がかなりあるのは、大陸棚地域である。しかし、これまた海の面積からすれば、その面積の割合は小さい。日本は1987年に、沖の鳥島のような小さな岩礁をコンクリートで固め、チタンの蓋をし、さらに行政的には東京都に属しているのに、それを国の直轄管理(1999年6月24日から)にまでして、200海里領海(排他的経済水域)を確保しようとしている。
残りの外洋の生産力は大変に低いので、大量にそこから魚を獲ることは期待できない。
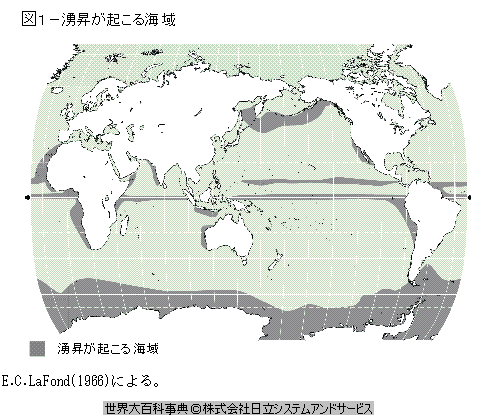
図1-9 湧昇が起こる地域(Web版世界大百科(日立システムアンドサービス)
http://ds.hbi.ne.jp/netencyhome/index.html
)
もうひとつ、aとも関係するが、どういう魚を食べるかという問題もある。どうしても魚は、陸上の家畜のように、〔太陽エネルギー〕→〔穀物〕→〔家畜〕と2段階というわけにはいかない。〔太陽エネルギー〕→〔植物プランクトン〕→〔動物プランクトン〕→〔小型の魚〕→〔中型の魚〕→〔大型の魚〕と食物連鎖の段階が多くなる。
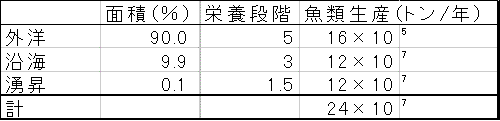
表1-1 各々の海域の生産力:ライザー(1969)の見積もり
外洋の生産力は著しく低い
マグロ・ブリ(ハマチ)のような大型の魚(高級魚)は食物連鎖の上の段階にある。この問題の一つは、食べたものがすべて体(肉)にならない、つまり食物連鎖の上に行くほど太陽エネルギーの利用ということを考えるとその効率が落ちるということ、もう一つは、食物連鎖の段階の上に行くほど汚染物質が濃縮する可能性が高いということである(生物濃縮、5・1(1)の補足)。そういうことを考えると、養殖のハマチを食べるより、できるだけ、そのエサとなるイワシを直接食べた方がいいということになる。
さらに、欧米人には評判の悪いクジラ食を考える。クジラは大きく分けて、ナガスクジラのような「ヒゲクジラ」と、マッコウクジラのような「歯クジラ」に大きく分けられる。このヒゲクジラはおもにオキアミなどのプランクトンを食べている。すなわち、食物連鎖の段階が小さいので太陽エネルギーの利用効率、あるいは汚染物質の濃縮ということを考えると、非常に有利だとわかる。もちろん、ヒトがオキアミを直接獲って食べてもいいのだが、広い範囲に散らばって生息しているオキアミを集め回るより、クジラに獲ってもらって、そのクジラを捕まえる方が効率が高いだろう(オキアミが食糧として向いているかは別として)。現在ナガスクジラの数がすごく減っているのは事実だろうから、当分保護して、資源として利用できるまで回復したら、厳重な管理のもとに利用するのがいいと思う。家畜を殺すのはいいが、野生動物を殺すのはダメという論理には納得できない。
※ 商業捕鯨は1988年に全面禁止になったが、じつは日本はまだ捕鯨を行っている。
一つは、国際捕鯨委員会(IWC)からも認められている沿岸捕鯨である。日本政府はツチクジラ(歯クジラ)66頭、ハナゴンドウ(歯クジラ)20頭、マゴンドウ(歯クジラ)50頭、タッパナガ(コビレゴンドウ、歯クジラ)36頭という制限を設け(2006年)、それに従い、網走(北海道)、鮎川(宮城)、和田(千葉)、太地(和歌山)、函館(北海道)の5つの港で細々と捕鯨を続けている。
例えば、和田港の捕鯨は南房総いいとこどりhttp://www.mboso-etoko.jp/cgi-bin/co_kaniHP/info.asp?uid=278&p=51参照。
ゴンドウクジラはふつうはイルカと呼ばれる方に入る。クジラとイルカの本質的な違いはない。歯クジラのうちの小型のものをイルカということが多い。
もう一つは「調査捕鯨」という名目で、2005年/2006年〜2010年/2011年には、ミンククジラ850頭±10%、ザトウクジラ50頭、ナガスクジラ50頭の捕鯨を予定している。ただし、最初の2年間はミンククジラ以外は、ザトウクジラ0頭、ナガスクジラ10頭の予定。日本捕鯨協会http://www.whaling.jp/qa.html参照。
※ さらにIWCは「生存捕鯨」(この言葉からして不遜な感じがする)というものも認めている。先住民が生きてゆくために必要な捕鯨を、地域と捕獲枠を制限して認めているもので、水産庁によるとロシア・チュコト地方がコククジラ(ヒゲクジラ)を年間140頭、米国・アラスカがホッキョククジラ(ヒゲクジラ、生きた化石といわれる)を同51頭、デンマーク領グリーンランドがミンククジラとナガスクジラを同184頭などである。
※ クジラの分類は、例えば岩手県山田町鯨と海の博物館http://www.town.yamada.iwate.jp/kujirakan/syurui/index.html参照。
f アメリカの影
現在、食糧(穀物)を安定して輸出に回せる国は限られている。それはアメリカやカナダなどの先進国である。例えばアメリカはアフガン紛争(1979年〜1988年)のとき、アフガニスタンに侵攻したソ連に対する圧力として、穀物を武器として使ったことがある(1980年)。慢性的な穀物の不作に悩んで、大量の穀物の輸入を続けている旧ソ連に対して、穀物の禁輸措置をとったのである。しかし実際は、有効な措置とはならなかった。当時「穀物メジャー」といわれた会社(アメリカのカーギル社(非上場企業としては世界最大の売上高を誇る、創業者のカーギル家・マクミラン家がすべての株を保有),コンティネンタル・グレーン社,フランスのルイ・ドレフュス社,オランダのブンゲ社,スイスのアンドレ社の5社を指すが、実際は多国籍企業で本社はすべてアメリカにある)が、海外の子会社を使ってソ連に穀物を売ってしまったのである。
教訓は二つ、一つはアメリカはいつでも穀物を「武器」として使うことができること、もうひとつは「石油メジャー」よりさらに実態が不透明な「穀物メジャー」が、実際の穀物の流通を支配しているということである。
その後、ルイ・ドレフュス社の一部を買収したADM社(アメリカ)が急成長して取扱高第2位に、またコンチネンタル・グレーン社も穀物部門を1998年にカーギル社に売却している。このように企業間の競争も激しいが、いずれにせよ、これら穀物メジャーが世界の穀物取引の70%〜80%を扱っているといわれている。